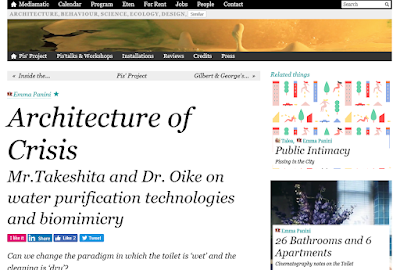さすがアムステルダム、というべきか。 挑戦的な企みが根っから好きなのでしょう。 取材から記事までがとても速かった。 実は最初、「Architecture of Crisis(危機の構造)」という見出しを見て、ピンとこなかった。しかし後からじわじわきた。なるほど、たしかに「危機の構造」だ。 水不足という危機によって洗い出される社会の構造。それに立ち向かおうとする人々のネットワーク。そして、解決に向けた取り組みを支える、あたらしい社会構造。 それがFILTOM。 なるほど。 Supported by Chitose Ohchi . Finally the FILTOM got on voyage. We set the challenge in Japan, but the article writer was from Amsterdam. And more, the writing speed was really fast. I firstly couldn't understand about the title of the article by EM MA san, "Architecture of Crisis". But soon later, I felt excited little and little. Yes, it's the Architecture of Crisis. The social architecture that the crisis of water shortage clarifies. The network of people who try to solve the crisis. And new social infrastructure which can help the activities. One of the infrastructure is the FILTOM. Interesting... Thank you very much for your rapid communication, EM MA san. And Also, BIG thanks to Chitose Ohchi , a cur...